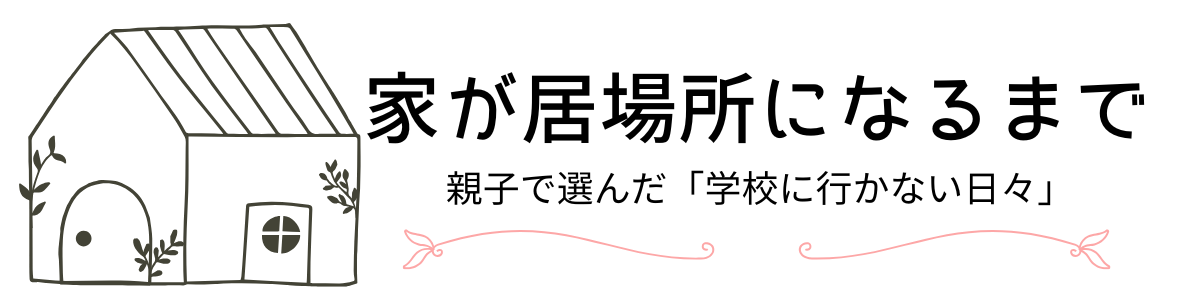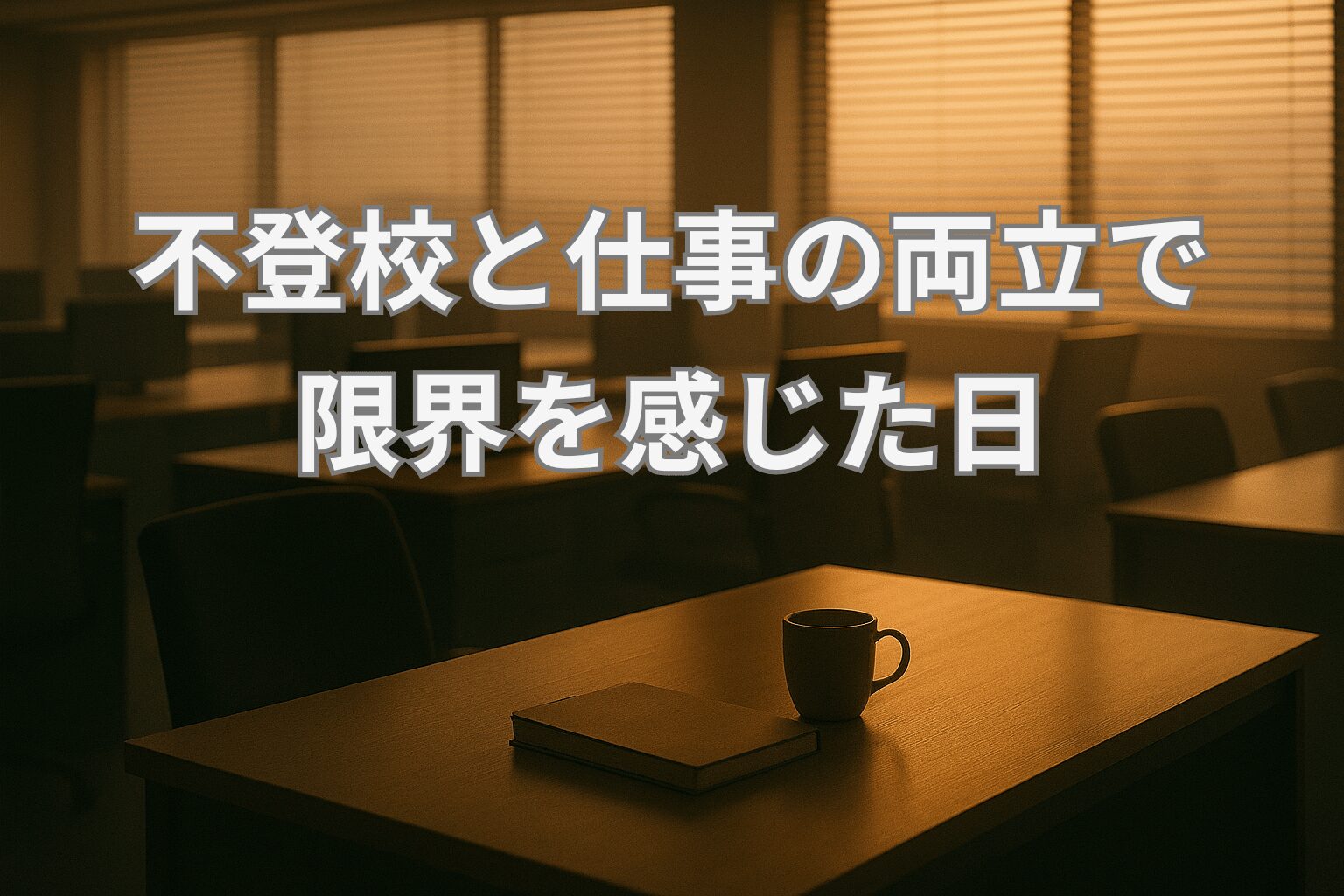WISC検査とは? 不登校の娘が受けた結果と見えてきた特性と気づき

娘の不登校をきっかけに、私は教育相談で「WISC検査」を紹介されました。
当時の私は「子どもの特性を知るヒントになるかもしれない」と思い、検査を受けることにしました。
実際に受けてみると、数字そのものよりも「理解の材料」として大きな意味がありました。
- WISC検査とは何か(診断との違い)
- 娘のWISC検査の結果と見えてきた特性
- 結果を踏まえて行った工夫と気づき
- 不登校の子どもと向き合う上でのヒント
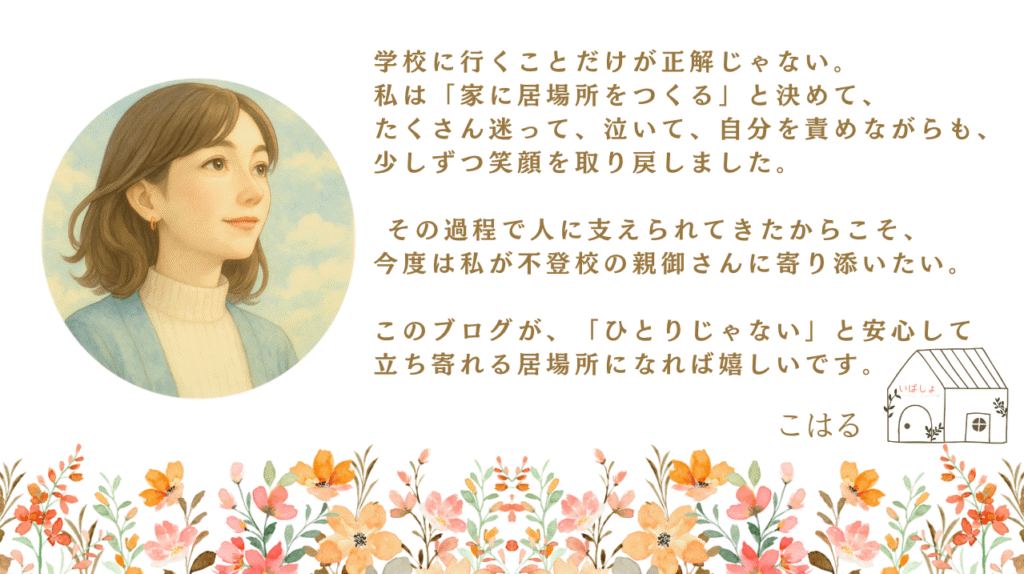
WISC検査とは?
「WISC(ウィスク)検査」という言葉を聞いたことはありますか?
学校や教育相談で紹介されることもある心理検査で、子どもの 「得意・不得意」 を知るためのものです。
よく「発達障害の診断ですか?」と聞かれますが、そうではありません。
診断をするためではなく、学習や生活の中でつまずきやすい部分、伸ばしやすい力 を把握するための検査です。
娘がWISCを受けるまで
不登校がはじまり一年が経った頃の小4秋。
私は一度、「発達障害の診断を受けるべきか」と考えていました。
というのも、幼いころから「ちょっと特性があるのかも」と感じていたからです。
- おもちゃが片付けられない
- 服は脱ぎっぱなし
- ゴミをそのまま放置
- 言われたことをすぐに忘れる
最初は「まだ小さいから仕方ない」と思っていました。
でも下の子が2歳くらいの時、自然にゴミを片付ける姿を見て「年齢のせいじゃない」と気づきました。
そこで、おもちゃにマークを貼って片付けやすくしたり、身支度ボードを作って朝の流れを可視化したり。
一度に指示を出さず、「今日はこれから3つやるよ」「まず一つ目は…」と段階的に声かけするよう工夫しました。
暴れたり強い癇癪を起こすことはありませんでしたが、とにかく生活面で手がかかる子。
「これは発達特性かもしれない」と思い、そういう前提で接する方が私自身も気が楽になりました。
「なんでできないの?」ではなく
「特性だから仕方ない」と思えば、余計なイライラをしなくて済むからです。
教育相談でこの気持ちを話したとき、職員の方から「一度WISC検査を受けてみませんか」と提案されました。
正直、娘にどう伝えるかは迷いました。
「遊べると思って行ったらテストだった!」となれば裏切りですし、かといって「発達障害があるか調べる」とストレートに言うこともできません。
そこでこう伝えました。
「今日は、いつもとはちょっと違う心理テストを受けるよ。学校のテストみたいに点数で決まるものじゃなくて、あなたの得意や好きなことをもっと知るためのものだからね。」
娘は「へぇ〜」と素直に受け入れてくれました。
娘のWISC検査の結果
結果は「全体的に平均」でした。
けれど、その中には娘らしい特徴がはっきりと出ていました。
言葉の理解は得意
語彙が豊富で、自分の考えを整理して説明する力が強いと分かりました。
確かに、日常でもニュースや本の言葉を大人顔負けに使うことがあり、思わず笑ってしまうことがあります。
豆知識や動物の生態など、自分で調べたこともよく覚えていて、いつも色々と話してくれます。
「なんでそんなこと知ってるの?」と驚かされることもしばしばです。
図形やスピードは平均
図形を見て考えたり、作業の速さは普通。
ただ、急かすと焦ってミスが増える傾向があるそうです。
「早くして!」と急がせるより、ゆったりと見守る方が力を発揮できるタイプ。
短期記憶(ワーキングメモリー)は苦手
一度に複数のことを覚えるのが難しく、板書や暗算が負担になりやすい。
これを聞いたとき、「ああ、だからか」と腑に落ちました。
漢字の書き取りが大嫌いで、家でも「三つ言うと一つは忘れる」「さっき言ったのに…」が日常茶飯事。
努力不足ではなく、“特性” だったんだと理解できた瞬間でした。
数字の結果を見た時よりも、「あ、うちの子の“生きづらさ”の理由がわかった」 と感じたことが何より大きかったです。
「できない」の裏には必ず理由がある。
それが分かるだけで、親としての心の重さが少し軽くなりました。
結果から見えてきた工夫
WISCを受けたことで、私は「やっぱり思い込みではなかった」と確信できました。
そして、学校に「こういう特性があるので、こういう配慮をお願いします」と、具体的にお願いできるようになったのです。
当時の私は、不登校の原因と考えられるものを一つずつ取り除いてあげたいと思っていました。
だから「弱い部分をサポートすれば、娘もまた学校に行けるようになるかもしれない」と期待していたのです。
実際、子どもによってはそうした配慮で登校できるようになるケースもあると思います。
ただ、娘の場合はそれが決定的な原因ではなく、後になって「そもそも“学校”という場所が合わない」という結論に行き着きました。
結果的に、WISCの数値を踏まえて工夫しても不登校が改善することはありませんでした。
でも、だからこそ私はこう思えたのです。
「特性のせいで学校に行けないのではなく、この制度そのものが合わないんだ」 と。
WISC検査は登校を促す解決策にはならなかったかもしれません。
けれど、「我が子に合わないものは何か」に気づけたという意味で、大きな一歩になったのです。
そして今振り返ると、こうも思います。
子どもによっては、検査結果をもとに工夫することで登校につながる場合もある。
うちの子のように、制度そのものが合わないと気づくためのきっかけになることもある。
どちらにしても、WISC検査を受けることは「理解を深めるためのきっかけ」にはなり得ると思います。
だからこそ、迷っている親御さんには「子どもを知るための一歩」として、前向きに考えてみてもいいのでは、と今は感じています。
まとめ──WISC検査を受けて感じたこと
- WISCは発達障害を診断するためのものではなく、子どもの得意・不得意を知るための検査
- 娘の場合は「言葉の理解は得意」「ワーキングメモリーは苦手」という特性が見えた
- 結果を数字で示せたことで、学校への説明がしやすくなり、サポートのお願いもしやすくなった
- 当時は「原因がわかれば登校できるかもしれない」と思ったが、結果的には改善にはつながらなかった
- それでも「学校制度そのものが合わない」と気づくことができたのは、大きな一歩だった
WISCを受けたからといって、すぐに不登校が解決するわけではありません。
でも、子どもの特性を知ることは「親が無駄に責めないための材料」になり、また「学校に説明しやすい根拠」にもなります。
最後に、同じように悩む親御さんへ
もしかしたら、WISCの結果が登校のきっかけになる子もいるかもしれません。
一方で、うちの子のように「制度が合わない」と気づくためのきっかけになることもあります。
どちらにしても、WISCは子どもを知るための一歩 です。
解決の答えそのものではなくても、子どもと向き合うための道しるべにはなります。
「この子にはこんな力がある」
「ここは工夫して支えればいいんだ」
そう思えるだけで、親の心は少し軽くなります。
どうか数字に振り回されず、「理解を深める材料」 として前向きに活用してみてくださいね。
補足として
なお、小6になった現在は、娘自身が「精神科に行きたい」と希望したことをきっかけに受診し、ADHDの疑いが強いと診断を受けています。
ただ、WISC検査そのものは「診断」ではなく、子どもの特性を知るための一つの材料として役立った、という思いに変わりはありません。