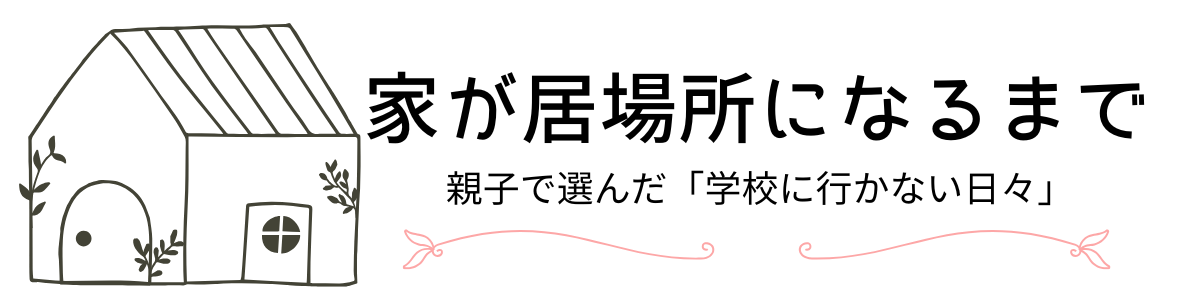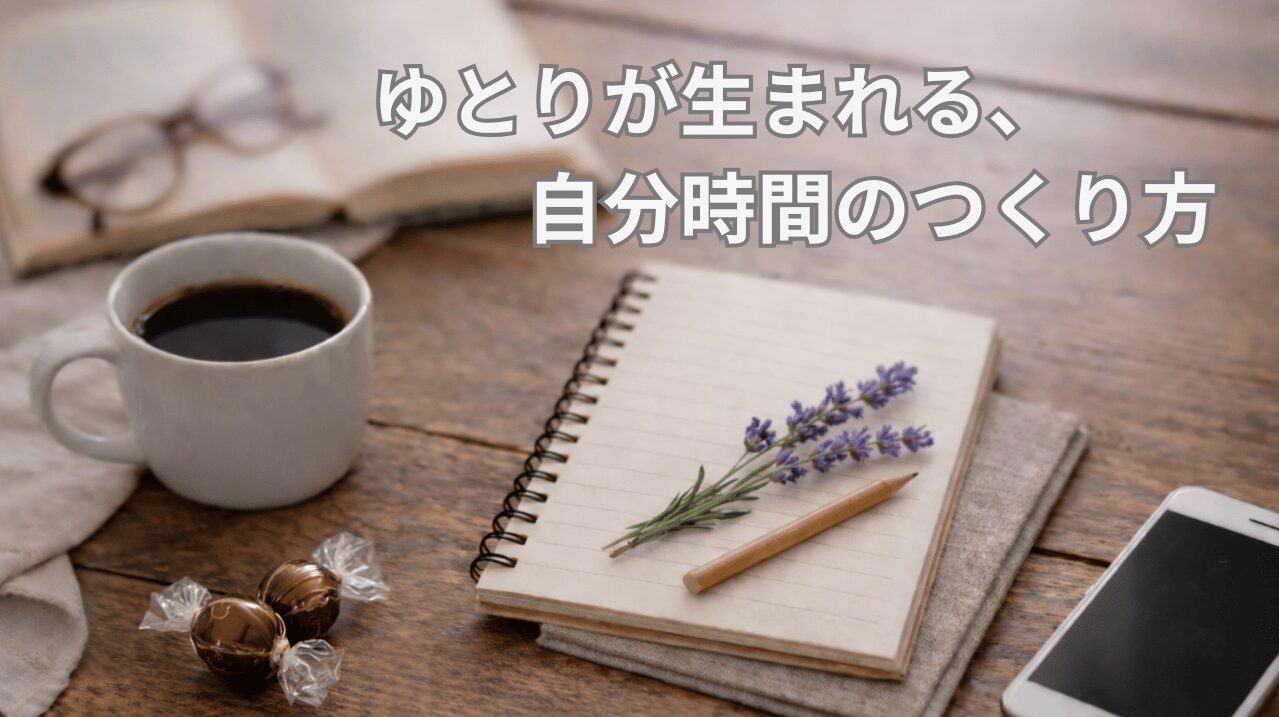【不登校の親へ】できていないことばかり見ていた私が気づいた“本当に大切なこと”

学校に行かない日々が続くと、
「このままで大丈夫だろうか」と不安になりますよね。
私もそうでした。
子どもの心を守るために、「もう無理に学校へ行かせない」と決めた。
それでも、“できていないこと”ばかりが気になって、子どもの将来を心配する毎日でした。
けれど、 できないことではなく、「できていること」に目を向けてみたら、
子どもの笑顔も、私の心も、少しずつ変わっていきました。
同じように悩むあなたにも、
そんな視点が、小さな安心につながれば嬉しいです。
不登校の子を前に、「このままで大丈夫?」と不安だった日々
”できないこと”ばかり目についていた
娘が学校に行かなくなってから、
私はずっと“できていないこと”ばかりに目を向けていました。
勉強が遅れている。
友達と遊んでいない。
昼夜が逆転している。
焦りや不安が積み重なっていくたびに、
「このままで大丈夫?」と不安になり、憔悴する日々でした。
娘を責めたいわけじゃない。
ただ、“ちゃんとした未来”を歩んでほしい――
その思いが、いつの間にかプレッシャーに変わっていたのかもしれません。
不安は”愛情の裏返し”だった
どんなに不安になっても、私は過去の経験から、
”娘を無理に学校に行かせない”と決めていました。
けれど、不安を押し殺すだけでは、自分の心がすり減っていくばかり。
どうしてこんなに不安なんだろう。
そう問いかけたとき、ふと気がつきました。
私はただ、娘に幸せになって欲しい。
それだけでした。
この不安は愛情の裏返し。
娘を信じたいのに、どう支えればいいかわからなかっただけ。
けれど、娘の人生は娘のものです。
私がコントロールするものではない。
私がどんなに娘の幸せを願い、その道に進むレールを敷いても、
その上を歩くかどうかは、娘が決めること。
そのことに納得できたら、不思議と不安は薄まっていきました。
「できていない」じゃなく、「できている」に目を向けてみた
小さな”できている”に気づいた日
できていないことばかりに目がいき、ある日、減点方式のように娘を見ていたことに気が付きました。
けれど、娘がリビングで笑っているのを見て、ハッとしました。
学校には行けていないけれど、
好きなゲームやアニメの話で家族と笑い合っている。
「笑える」って、すごいことかもしれない。
そう思った瞬間、胸の中が少しだけ温かくなりました。
それから私は、手帳に娘の“できていること”を書き出してみました。
- 「おはよう」と自分から挨拶をしてくれた
- 「ねぇ、ママこれ見て」と自分から話しかけてくれたこと
- 好きな絵を夢中で描いていたこと
たったそれだけのことが、
いつの間にか“希望のリスト”になっていました。
親の“できたこと”も数えてみる
「子どもがちゃんとできていない」と思うたび、”ダメな親だ”と責めている自分がいることにも気が付きました。
だからこそ、私自身もできたことを数えるようにしてみました。
- ご飯を作った
- 仕事に行った
- 「学校に行かなくていいよ」と言ってあげられた
- 子どもと笑い合えた
どんな小さなことでもいい。
親として当たり前だと思うことでもいい。
子どものことも、自分のことも、「それでいい」と認めることにしました。
不登校が解決したわけじゃない。
それでも、昨日より穏やかに過ごせたという事実が、
私の心を少し軽くしてくれました。
学校に行けなくても、“学ぶ力”は日常の中で育つ
好きなことを通じて、つながりが戻った
我が家では、うさぎを飼っています。
娘が不登校になる少し前に、飼いたいと言い出しました。
今思えば、この頃から不安定だったのでしょう。

私は正直反対でした。
命に責任を持つ重さも、経済的にも決してラクではないことを知っていたからです。
そこで私は、『うさぎの飼い方の本』を渡して、
「正しい知識をつけて飼えると、ママを説得できたらいいよ」
と答えました。
頭ごなしに自分の価値観を押し付けるのではなく、
娘の意見も聞き、議論できるように働きかけました。
そして、この頃は行き渋りが始まった頃で、
たまに登校した際も、この本を読んでいたそうです。
そして、いつしか『うさぎの飼い方の本』は、付箋だらけになっていました。

興味の先にある“学びの芽”を、そっと見守る。
「ねぇママ、うさぎってね…!」
目を輝かせて話す娘を見て、私はハッとしました。
ちゃんと“学ぶ力”は、生きていたんです。
学びは、教科書の中だけじゃない。
「必要だから学びたい」と感じて、自分で調べて、知ろうとしていた。
“興味を持って調べる力”
“自分で学びを深める力”
それが、ちゃんと育っていることに気づいたとき、私は少しだけ安心できました。
”好き”は、学びの入口
結局、娘の熱意に負けて、うさぎを飼うことになりました。
うさぎのお世話から、娘は食事や気温にも興味を持ち、
図鑑を調べたり、日記を書いたりするようになりました。
それはまるで、「学び直す力」を取り戻していくようでした。
好きなことを通じて心が動くとき、
人は自然と前を向ける。
その姿を見て、私は「焦らなくていい」と
やっと心から思えるようになりました。
今、悩むあなたへ—焦らなくても大丈夫
不安を否定しなくていい
「このままでいいの?」と悩む気持ちは、
子どもを思うからこそ生まれる自然な感情です。
その不安も否定せず、
”親として、ちゃんと向き合っている証拠だよ”と
自分自身で受け止めてあげてください。
自分を責めなくていいんです。
「学校に行かない」ことは、「怠惰」ではありません。
「学校に行かせない」ことも、「逃げ」ではありません。
小さな「できたね」を積み重ねていこう
「そんな事言われても、不安は消えない」
そう思いますよね。
私も最初からうまくできたわけではありませんし、
すぐに受け入れられたわけでもありません。
今も、すべての不安や悩みがなくなったわけでもありません。
子どもが笑えたこと。
あなたが笑顔で話しかけられたこと。
少しずつ、“できていること”を見つけながら歩いてきました。
それだけで、少し前に進めている気がします。
焦らなくて大丈夫。
今日も、小さな「できたね」を見つけていきましょう。
きっと笑い合える日がやってきます。

それでも、「安心できる家庭」を少しずつ築いていこうと決めた。
最後に…
最近、私が印象に残ったセリフを紹介します。
親がどれだけ心配しようが、子どもはいつか勝手に飛んでいくものです。
こちらにできるのはせいぜい、うまい落ち方を教えることぐらいですよ。
引用:アニメ『ヴィジランテ』第9話 ナックルダスターのセリフより