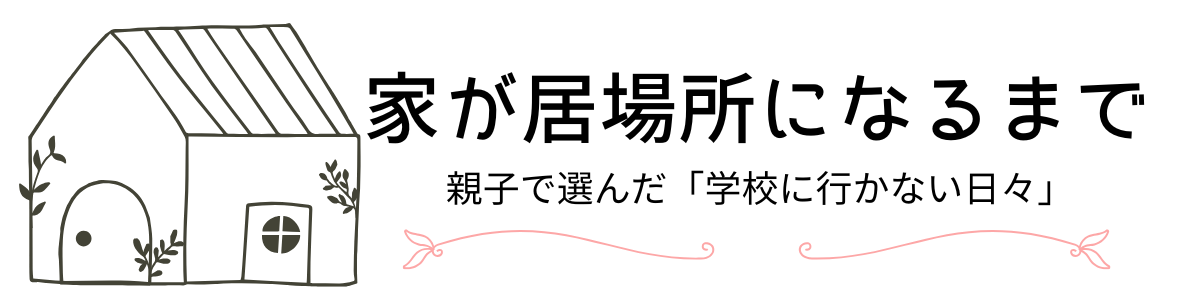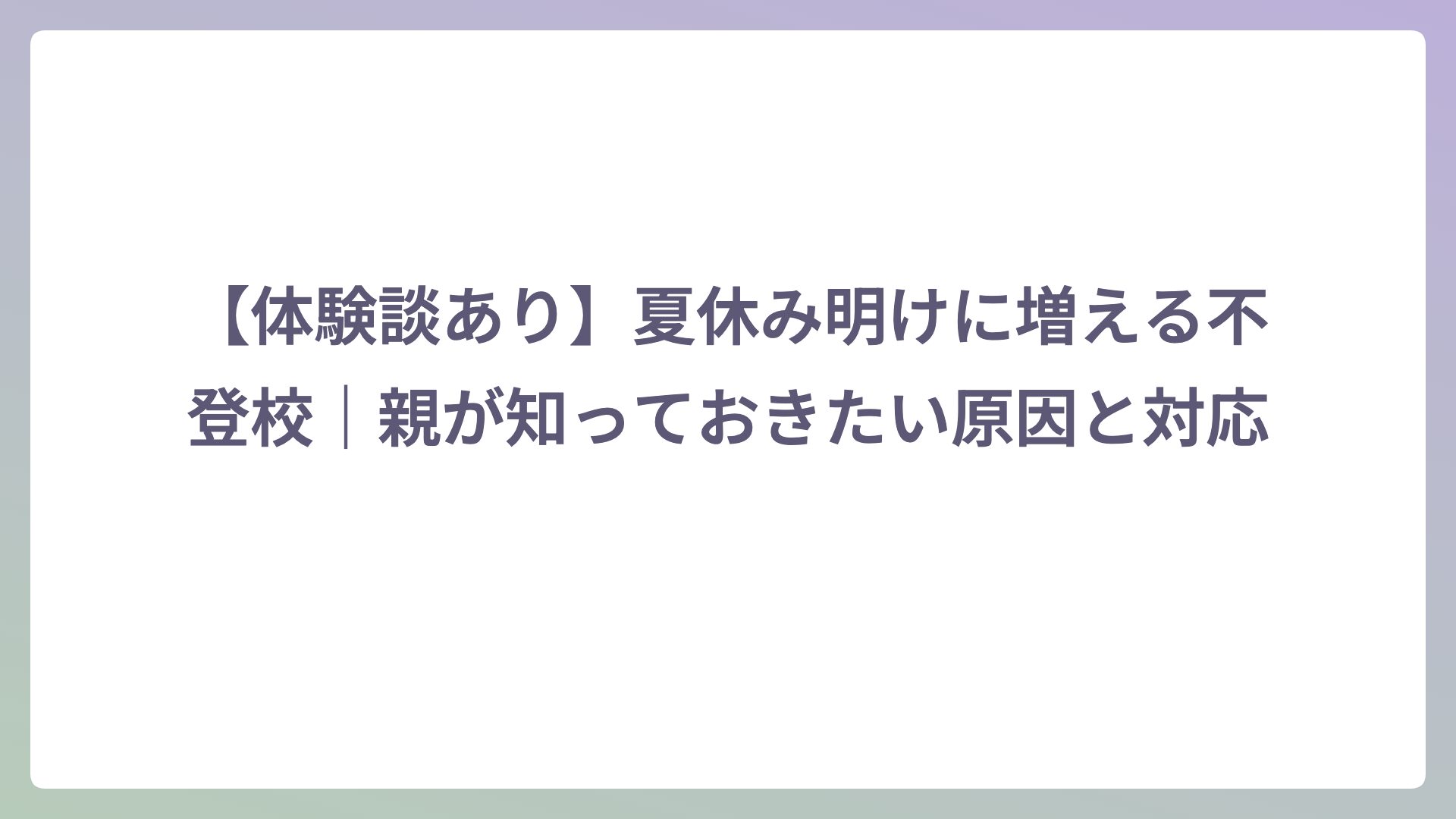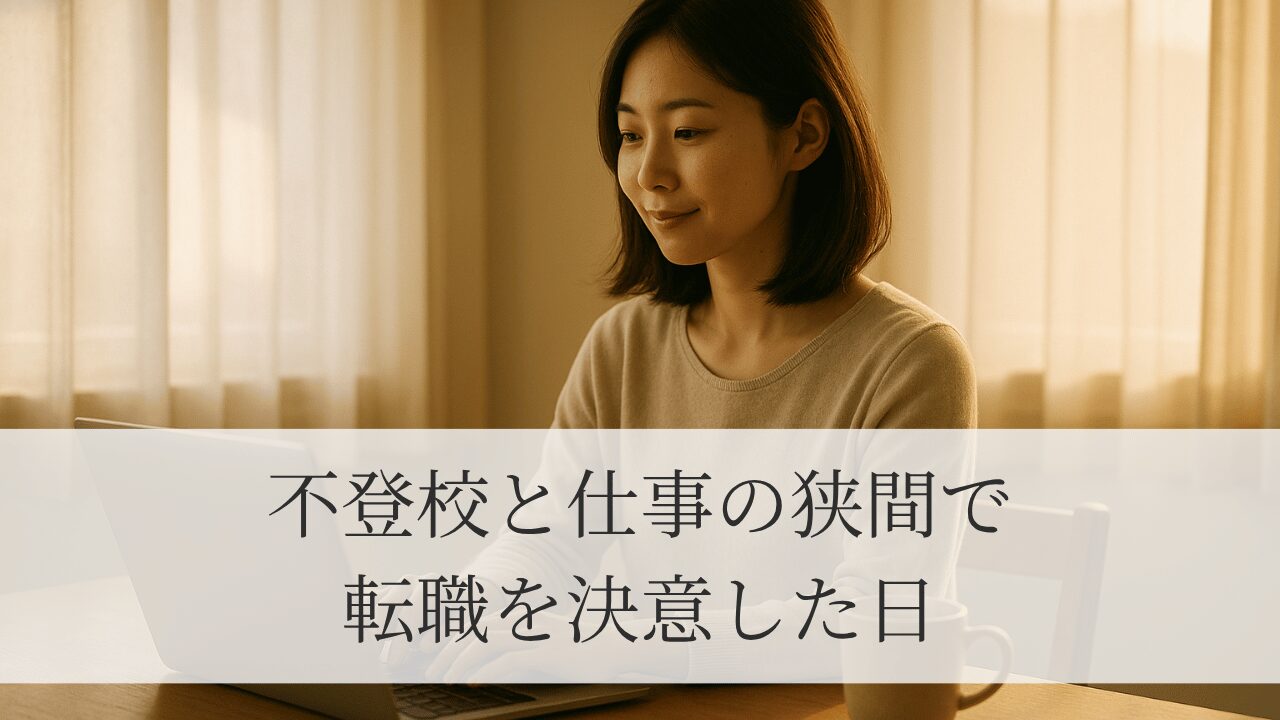不登校で勉強しない子に悩む親へ|手放したら見えた“学びの力”
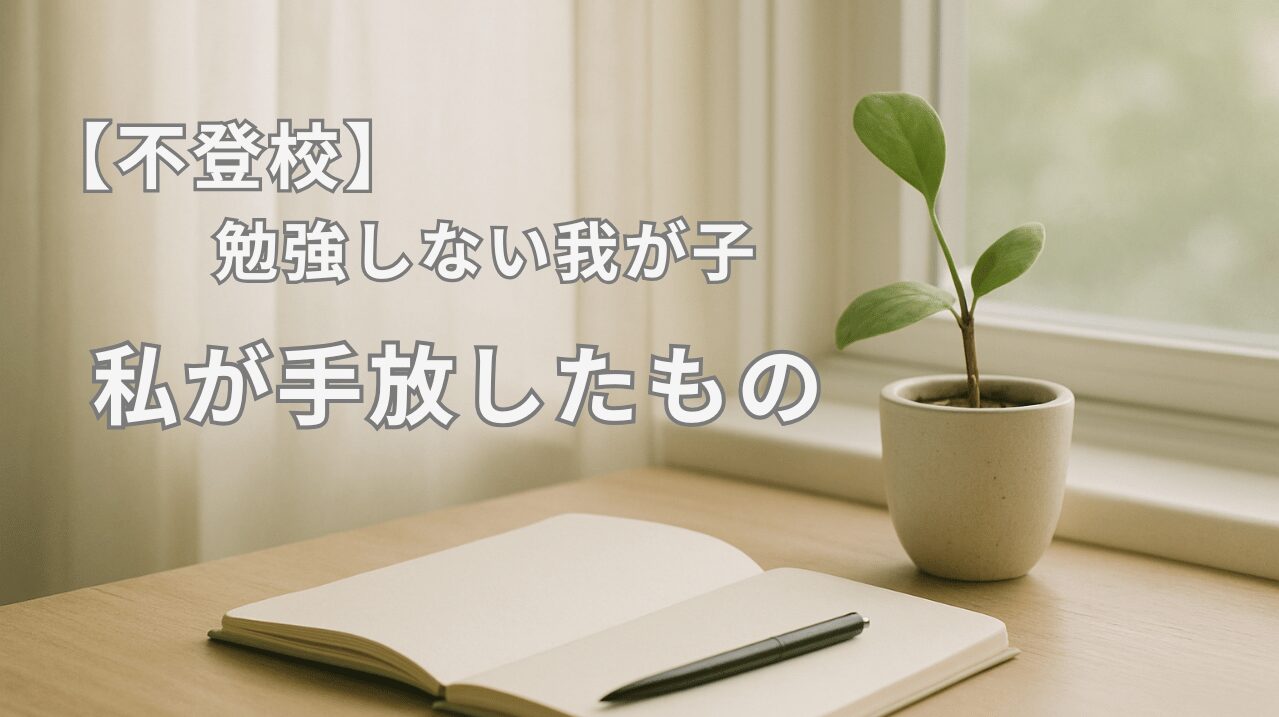
「毎日YouTubeやゲームばかりで…このまま勉強についていけなくなるんじゃ?」
不登校のわが子を見て、そんな不安が胸をしめつけること、ありませんか。
私も同じでした。
“学ばせなきゃ”“このままじゃ将来が…”と焦るあまり、
勉強しない娘にイライラしてしまう自分がつらかった。
私が手放すべきだったのは、
“娘をコントロールしようとする自分自身”だった
と気づきました。
そこから、勉強しない娘の中にも、
ちゃんと「育っている力」が見えるようになったんです。
この記事では、
学校に行かない日々のなかで見えてきた
“学びは一つじゃない”という気づきをお話ししたいと思います。
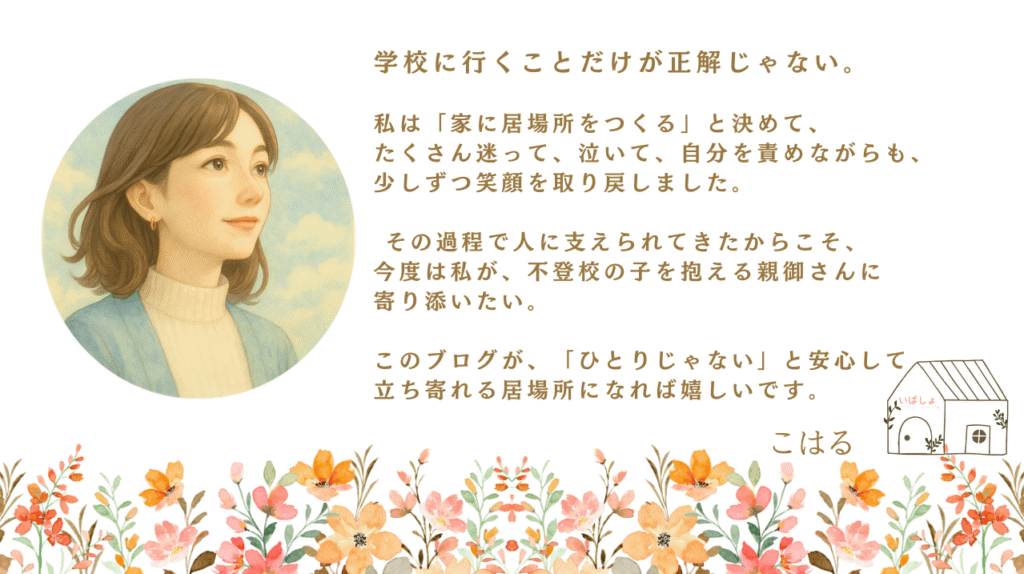
勉強していない姿に、イライラしてしまう
何もしない娘を見て、焦りが膨らんでいった
娘が小4、不登校になって半年ほど経った頃のことです。
仕事が思うようにいかなくなり、私自身に余裕がなくなっていました。
そのせいか、学校に行かない娘に対して、苛立ちをぶつけてしまう日もありました。
朝は起きず、勉強もしない。
気づけば一日中ゲームや動画。
そんな娘の姿を見るたび、胸の奥でイライラと不安が膨らんでいきました。
「私はこんなに必死なのに、どうして好きなことだけしていられるの?」
「みんな頑張って学校に行っているのに…」
そう思えば思うほど、焦りだけがどんどん大きくなっていきました。
イライラの正体は「未来への不安」だった
当時の私は、とにかく不安でいっぱいでした。
「このまま大人になって、漢字が読めなかったら?」
「計算できなくて仕事で困るんじゃない?」
「九九も怪しいのに、この先もっと差が開いてしまうのでは…?」
頭の中は“未来への恐怖”で埋め尽くされていたのです。
だから私は、
「なんとかしなきゃ!」
と躍起になっていました。
けれど、目の前の娘はそんな私の不安など意に介していないようで、
“なんで伝わらないんだろう”という焦りだけが、私の中で大きくなっていきました。
「こんな気持ちになるのは私だけ?」
当時の私は、いつもそんなふうに自分を責めていました。
無理にやらせても、何も変わらなかった
勉強させようとしても、全く続かない
娘が勉強さえしてくれれば、私のイライラはおさまるかもしれない。
そう思い、小4の娘に、2年生レベルのドリルを買ってきて、
「国語と算数、一日1ページだけでいいからやって」
と伝えました。
けれど、そんなもの続くはずもありません。
ご褒美で釣ってみても効果はゼロ。
そして私は、さらにイライラしました。
「なんで言うこと聞いてくれないの?」
「なんで私の心配が伝わらないの?」
この時ようやく気づいたのです。
“私の気持ちをわかってほしい”
という思いが伝わらず、自分をイライラさせていたということに。
「本人が必要だと思わないと意味がない」と気づいた日
私は離婚してから、簿記やFPの資格を取りました。
子どもたちを守るためには知識が必要だと感じ、
“自分の意思で” 勉強を始めたのです。
その経験から、ふと気づいたことがあります。
「人は、自分が必要だと思った時にいつでも学ぶことができる」
ということに。
私が娘にやらせようとしていたことは、
”今の娘にとって必要ではない”のです。
必要性を感じていない娘に無理をさせても、
意味がない——むしろ逆効果。
「まぁいいか。勉強なんて後からでもきるし」
そう思えた日は、私にとっての転機でした。
好きなことの中に、“学ぶ力”はちゃんとあった
ゲームのプレゼンで見えた「調べる力」「まとめる力」
ある日のこと。
娘が「このゲームが欲しい」と突然言ってきた時のことです。
誕生日もクリスマスも近くない。
特に頑張ったこともなく、ご褒美もない。
でも、頭ごなしに「ダメ」と言うのは違うと思い、まずは理由を聞いてみました。
すると娘は、
動画で見て楽しそうだった、
時間つぶしになるから
と、自分にとってのメリットだけを述べました。
そこで私は伝えました。
「それじゃママは財布を開かないよ。
なぜ、欲しいのか、どんないいことがあるのか、ママが納得できるようにプレゼンしてごらん。」
チャットGPTを使ってもいい。
Canvaを使って資料にしてもいい。
そう伝えると、娘の目の色が変わりました。
娘のプレゼンが教えてくれたもの
完成したプレゼン資料は、10枚にわたっていました。
正直いうと、文章の多くはAIをそのままコピペしていたのが丸わかり。
でも、そこには娘の“本気”が詰まっていました。
そして、その資料を形にするまでのプロセスには、
- 説得力をつくる見せ方の工夫
- 必要な情報を調べる力
- 記事を引用してまとめるコピー&ペーストの技術
- Canvaで構成を考えるデザイン力
こうした“生きる力”が、しっかり含まれていたのです。
「ただ欲しい」を「どう伝えたらいいか」に変える力が育っている。
私はそう感じました。
机に向かわせても全く動かなかった娘が、
好きなことのためなら、こんなにも集中している。
勉強ではなくても、
好きなことの中には「学びの芽」がある。
無理に机に向かわせていた頃より、
娘の目はずっと生き生きしていました。
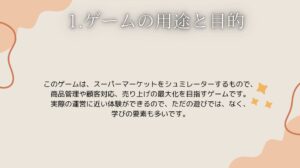


イライラの原因は、子どもじゃなく“私自身”だった
コントロールしようとするほど苦しくなる
私はずっと、
「娘が勉強しないからイライラしている」
と思い込んでいました。
でも本当は違った。
私が娘をコントロールしようとして、
思い通りにならないから苦しかっただけ。
「学校に行かないと将来困る」
「勉強しないと遅れる」
そういう不安を理由にしながら、
私は娘をコントロールしようとしていました。
そして、思い通りにならないからイライラする。
……原因は娘ではなく、
**“娘を自分の枠にはめようとしていた私自身”**だったのです。
子どもは子どもの人生を生きている
娘の人生は、娘のものです。
親であっても、それをコントロールする権利なんてない。
そう思えるようになったとき、少しだけ気持ちが軽くなりました。
学校に行かなくたっていいじゃん。
勉強なんて、家でできるし、友達だって作れる。
勉強しなくたっていいじゃん。
好きなことの中から、遊びの中から、学ぶことだってある。
必要だと感じたら、その時学べばいい。
苦労するかもしれない。
恥ずかしい思いをするかもしれない。
でも、それもその子の経験。
私は、あとで困るよ、苦労するよと伝えた。
きっと届いていない。響いていない。
でも、いいよ。それで。
人生終わるわけじゃないんだし。
無理強いさせて、モヤモヤを抱えたまま過ごすことのほうが、
将来苦労することより、娘にとって辛いことなのかもしれない。
転んで擦りむいたくらい、放っておいても治る。
大怪我にならないよう、見守って、必要なら手を差し伸べればいい。
一見、冷たく聞こえるかもしれません。
でも、これは突き放しではなく、
「あなたと私は別の人間だよ」
「それでもいつでも味方だよ」
というメッセージそのものなんだと思います。
子どもがありのままを受け止められるというのは、
親の理想に合わせることではなく、
**“その子のペースと選択を尊重すること”**
なんだと、私は感じています。

今、悩んでいるあなたへ
勉強していなくても、何も失われていない
「勉強してない」「何もしてない」
そう見える日って、ありますよね。
私も毎日のようにそう思っていました。
でも実際は、子どもの中では
見えないところでいろんな力が育っていることに、あとから気づきました。
娘はいま小6です。
週に1度、オンライン塾で算数を学んでいます。
小2の内容からスタートして、
8ヶ月で5年生の終わりまで追いついてきました。
“卒業”という言葉が見えてきた頃、
娘自身が「このままじゃダメかも」と感じて、
少しずつ動き出したんです。(この話はまた別の記事で)
だから、どうか安心してください。
必要だと感じた瞬間に、人は学び始めます。
それは子どもも大人も同じです。
子どもの「好き」は、学びの入り口になる
私は娘に
「欲しいなら理由を考えてプレゼンしてみて?」
と伝えただけでした。(実際にはAIの力も借りつつ)
その過程は、
調べる・まとめる・伝える
という、これからの時代に必要な力へつながっていました。
“好き”は、学びの原動力。
これはどの子にも必ずあります。
親はただ、“環境と安心”を用意すればいい
無理に勉強させなくても、
焦らなくても大丈夫。
親が安心して見守る土台をつくれば、
子どもは自分のペースで、ちゃんと前へ進んでいきます。
大事なのは、子どもの意見を尊重すること、
イライラの原因を子供に押し付けないこと。
それだけで、グッと心は軽くなるはずです。
大丈夫。
あなたの子どもにも、あなた自身にも、ちゃんと“ゆっくり育つ力”があります。